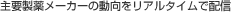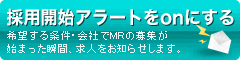先日、北里大学特別栄誉教授・大村智さんが放線菌の研究でノーベル生物学・医学賞を受賞したニュースが駆け巡りました。大村さんの同賞受賞は、1987年の利根川進さん、2012年の山中伸弥さんに続き、日本人としては3人目です。
先日、北里大学特別栄誉教授・大村智さんが放線菌の研究でノーベル生物学・医学賞を受賞したニュースが駆け巡りました。大村さんの同賞受賞は、1987年の利根川進さん、2012年の山中伸弥さんに続き、日本人としては3人目です。
大村さんの代表的な研究成果・イベルメクチンは、オンコセルカ症(河川盲目症)やリンパ系フィラリア(象皮病)の原因となる線虫を麻痺させ、増殖を抑えるマクロライド系抗生物質(マクロライド系といえば、身近なところではクラリスロマイシンなどが挙げられます)。放線菌から副作用が少なく抗菌スペクトルが広いことで知られています。
放線菌は、細菌の中でも有効物質を多く生成することで知られ、これまでも活発に研究が行われてきました。山中教授のiPS細胞と違ってその歴史は古く、結核治療薬のストレプトマイシンにまで遡ります。大村さんが、イベルメクチンの元になる新種の放線菌をゴルフ場の土から発見した、というのは有名な話ですが、それは今から40年も前の1975年のこと。にもかかわらず、今になってなぜ受賞が決まったのでしょうか。
『榎木英介のサイエンス&メディアニュースウォッチ』で、病理専門医/科学・技術政策ウォッチャーの榎木さんは次のように語っています。
(今回の受賞について)WHOは即座に歓迎のメッセージを発表している。なぜWHOが歓迎するのか。それは、「イベルメクチン」が「顧みられない熱帯病」(neglected tropical disease)に含まれるオンコセルカ症(河川盲目症)やリンパ系フィラリア(象皮病)の治療に効果を示したからだ。(中略)ノーベル賞委員会は、今回の生理学・医学賞に、「顧みられない熱帯病」への関心を高めるという狙いを込めたと思われる。
“顧みられない熱帯病”とは、製薬メーカーが莫大な開発コストをかけて新薬を作っても、回収できる見込みのない途上国の疾患を指す言葉。リンパ系フィラリア症、シャーガス病、デング熱など17の疾患がこれに当たります。毎日新聞10月5日号によると、「米国で1995年からの10年間で承認された約1500種類の新薬のうち、途上国向けの感染症の薬は1・3%しかなかった」とされており、今後の医療の課題とされています。
イベルメクチンが、アフリカ・中南米で、薬を買うお金のない人も含む10億人以上の人々を救ったのは、大村さんが開発特許権を放棄し、製造元・メルクがWHOに同薬を無償提供したからです。大村さんの行動も素晴らしいものですが、利益を度外視しても途上国向け感染症薬に取り組もうとした製薬メーカー側の英断も、忘れてはなりません。
現在、製薬メーカーのこうした取り組みが報じられる機会はまだまだ少ないです。しかし、“顧みられない熱帯病”が、人々の健康を守りつつも利益を出さなければならないという製薬メーカーのジレンマに根ざしている以上、もっと多くメルクのような企業がメディアで取り上げられるようになれば、途上国への無償提供は企業のイメージアップにつながり、製薬メーカーがもっと熱帯病を顧みやすくなるのではないでしょうか。
改めて世界的に解決が望まれていると露呈した“顧みられない熱帯病”問題に対し、業界と各種メディアの連携が望まれます。大村さん受賞を喜ぶとともに、そんなことを思った今回のノーベル賞でした。
(文・栗山 鈴奈)